水質検査とは、水の色・においや硬度などの性質、有害な化学物質や細菌の有無などを調べ、使用目的の基準を満たしているか判定する検査のことです。検査場所や検査対象となる水の種類によって、検査項目や方法は多数あります。また検査を行う機関も数多くあり、対応や検査費用もまちまちとなっています。今回は飲料水やプール、公衆浴場など水質検査の種類ごとに、検査項目や検査基準についてご紹介します。ご検討の際の参考にしてください。
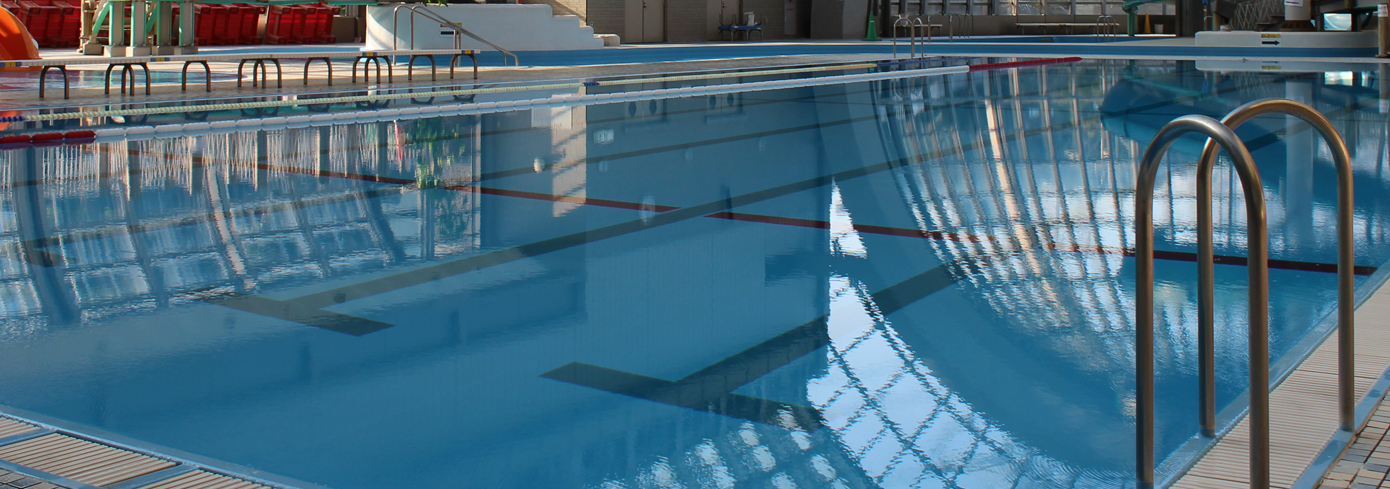
水質検査とは
水質検査の目的
水は、社会のさまざまなシーンで用いられており、私たちの暮らしに欠かせません。
水質検査は、水が使用される目的の基準に合致しているかどうかを測定するものです。検査の内容は、水の色やにおい、微生物・細菌の有無などで判定します。検査項目やその基準は、水の使用目的ごとに準拠する法令があり、それぞれで定められています。すべてが同一基準ではありません。
基準を満たさない水が用いられると、社会でさまざまなリスクが発生します。もっとも重要な被害は、人体への悪影響でしょう。飲料水が基準に合致しないまま使用されれば、深刻な健康被害が起こります。さらに、プールや浴場など、人が直接触れる水も感染症発症の原因となり、重大な健康被害をもたらすケースもあり、大きな影響が懸念されます。
水道法水質検査第20条に基づいたもの
水道法で定められた内容
水道水の水質基準は、「水道法」で定められています。
水道法(昭和32年6月15日法律第177号)は、水道事業について定める法律。その第2章「水道事業」第2節「業務」の中に、「水質検査」第20条があります。以下にその内容を抜粋します。
- 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
- 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
- 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
検査を実施する際は、水質基準に係る検査方法があり、基準項目(51項目)ごとに検査方法が決められています。
飲料水水質検査
日ごろ飲用する水道水が対象
私たちが日常的に飲んでいるのは、主に水道水です。人が飲用するものですから、もっとも高い安全性が求められます。ビルで使用されている飲料水の場合は、建築物衛生法で定められた水質検査を実施しなければいけません。飲料水として適しているかどうか、定められた項目について定期的に検査する必要があります。
飲料水の検査項目は水道法が51項目、建築物衛生法による飲料水の水質検査では、水道または専用水道から供給する水のみを水源として供給する場合、16項目+消毒副生物12項目となっています。基準値は一定の値以下であれば検出されても問題がないものから、わずかであっても検出されてはいけないものまで、項目ごとに定められています。
水道法では水道事業者、水道用水供給事業者おび専用水道の設置者は、水質検査計画を策定することが求められています。水質検査計画は毎事業年度の開始前に策定し、水質検査項目や検査頻度、検査箇所などをあらかじめ公表することになっています。
建築物衛生法による水質検査では、項目ごとに6カ月に1回、1年に1回などと検査頻度が定められています。項目によっては、2回目を省略できるものもあります。
なお、ビルでの給水では、水源が水道水や専用水道以外の場合は、検査項目や検査頻度が異なります。
「水道法」にもとづく水質検査項目と基準
| 検査項目 | 基準値 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1 ml の検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005 mg/L 以下 |
| セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01 mg/L 以下 |
| 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01 mg/L 以下 |
| ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01 mg/L 以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05 mg/L 以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L 以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01 mg/L 以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L 以下 |
| フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8 mg/L 以下 |
| ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 |
| ベンゼン | 0.01 mg/L 以下 |
| 塩素酸 | 0.6 mg/L 以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/L 以下 |
| クロロホルム | 0.06 mg/L 以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L 以下 |
| 臭素酸 | 0.01 mg/L 以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/L 以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L 以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L 以下 |
| ブロモホルム | 0.09 mg/L 以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L 以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0 mg/L 以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下 |
| 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下 |
| 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0 mg/L 以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下 |
| マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下 |
| 塩化物イオン | 200 mg/L 以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L 以下 |
| 蒸発残留物 | 500 mg/L 以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L 以下 |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/L 以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L 以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L 以下 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005 mg/L 以下 |
| 有機物(全有機炭素(TCO)の量) | 3 mg/L 以下 |
| pH 値 | 5.8 以上、8.6 以下であること |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
プール・公衆浴場などの水質検査
「遊泳場」「公衆浴場」によって、適用される基準は異なる
・一般遊泳用プール
一般遊泳用プールの水質は、どんな基準にもとづいているのでしょうか。厚生労働省では、不特定多数の人々が利用する施設を対象とした生活衛生対策の一環として、遊泳用プールの衛生水準を確保するための基準「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け厚生労働省健康局長通知)を設けています。この基準が適用されるのは、学校のプールを除くすべての遊泳プールです。
検査項目は7つ。基準や検査頻度は項目ごとに異なります。特に気をつけたいのは遊離残留塩素濃度です。病原菌発生を防ぐため検査頻度も多く、プール内で濃度が均一になるように管理を求められています。
なお、検査項目や基準については、プール施設の所在地の都道府県、政令市、特別区などの条例・要綱、最寄りの保健所による指導もご確認ください。
学校については、学校保健安全法(平成21年4月1日施行)の規程に基づく「学校環境衛生基準」(平成30年4月1日施行)及び「学校環境衛生管理マニュアル」(平成30年度改訂版)に従って管理します。
「遊泳用プールの衛生基準について」による遊泳用プールの水質検査項目と基準
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| pH 値 | 5.8 以上、8.6 以下であること | 毎月1回以上 |
| 濁度 | 2度以下であること | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 12 mg/L 以下であること | |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4 mg/L 以上であること。また、1.0 mg/L 以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
| (塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の二酸化塩素濃度) | 0.1 mg/L 以上 0.4 mg/L 以下であること | |
| (塩素消毒に代えて亜塩素酸により消毒を行う場合の亜塩素酸濃度) | 1.2 mg/L 以下であること | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
| 一般細菌 | 200 CFU/mL 以下であること | |
| 総トリハロメタン | おおむね 0.2 mg/L 以下であることが望ましい | 毎年1回以上(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
・公衆浴場
プールと同様にさまざまな人が利用する公衆浴場では、プールとは別の水質基準が設けられています。
この基準の対象となるのは、銭湯や健康ランドなど「温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場(一般公衆浴場・その他公衆浴場)」であり、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(令和元年9月19日付厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)によって指針が示されています。
検査項目やその基準は、「原湯(浴槽の湯を再利用せず、浴槽に直接注入される温水)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せず直接浴槽へ注入される水)、上り用湯及び上り用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓・水栓から供給される温水または水)」と「浴槽水」とで異なります。
また、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じる恐れがないときは、大腸菌、レジオネラ属菌以外の基準の一部又は全部を適用しないことができます。
なお、都道府県によっては、入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の観点から、条例で独自の検査項目や基準を設けている場合もあります。
「公衆浴場における水質基準等に関する指針」による浴槽水の水質検査項目と基準
| 検査項目 | 基準値 | 検査頻度 |
|---|---|---|
| 原湯、原水、上り用湯及び上り用水 | ||
| 色度 | 5度以下であること | 年1回以上 |
| 濁度 | 2度以下であること | |
| pH 値 | pH 値5.8~8.6であること | |
| 有機物(全有機炭素 (TCO) の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 |
有機物(全有機炭素 (TCO) の量)は 3 mg/L 以下、又は過マンガン酸カリウム消費量は 10 mg/L 以下であること。 (注)塩素化イソシアヌル酸、又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素 (TCO) の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10 mg/L 以下であることとする。 |
|
| 大腸菌群 | 検出されないこと | |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU/ 100 mL 未満) | |
| 浴槽水 | ||
| 濁度 | 5度以下であること | ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上 連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上) |
| 有機物(全有機炭素 (TCO) の量)又は過マンガン酸カリウム消費量 |
有機物(全有機炭素 (TCO) の量)は 8 mg/L 以下、又は過マンガン酸カリウム消費量は 25 mg/L 以下であること。 (注)塩素化イソシアヌル酸、又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素 (TCO) の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、25 mg/L 以下であることとする。 |
|
| 大腸菌群 | 1 個/mL 以下であること | |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10 CFU/ 100 mL 未満) | |
まとめ
水は人が飲用する場合や肌に直接触れる場合はもちろん、生活環境に存在する水はどれも少なからず人体へ影響があります。水の安全性を担保する水質検査は、とても重要な検査です。それだけに、検査に必要なコストも高額なものとなります。
最近では、水質検査のキットがネット通販で安価に販売されており、「社内で対応しよう」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、水の汚染による事故は規模が大きく広範囲になりがちで、検査精度の高さと信頼性は必要不可欠です。
また、水質検査の項目や基準などは、法律の改正や省令、通達などで絶え間なく変化しており、こうした情報をタイムリーに把握するには専任者の設置が必要になり、組織としての負担も大きくなります。
私たち日本メックスでは、水質管理者などの資格保有者が社内でスタンバイしています。水質検査に関する知識と経験を兼ね備えた、プロフェッショナルたちによる精度の高い検査を実施します。
「信頼できる検査機関はないか」とお考えなら、まずは私たち日本メックスにご相談ください。
(文:下村 亨、吉田 昇)