
デジタルの力によってビジネスを変革するデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)は、企業の共通の課題となっています。ところが、これまでに構築してきたレガシーシステムが足かせになり、DXが進まないというケースも出てきています。これに対し、経済産業省が、「レガシーシステムの課題が解決できなければ、2025年以降、日本経済も企業も大きな痛手を負う」と発表して話題に。本記事では、「2025年の崖」と呼ばれる危機と、その打開策となるデータセンターへのアウトソーシングについて解説。さらにデータセンターを活用する上で重要になる建物設備の保守についてご紹介します。
増大するデータトラフィックを支える
データセンター

近年、デジタル化とともにデータトラフィックが急増しており、それを支えるデータインフラの重要性が高まっています。特にデータセンターは、日々生成される大量のデジタルデータを格納・処理する役割を担っており、その存在なしでは企業活動を営むのが難しくなっています。止まることが許されない企業活動を支えるために、高い信頼性を持ったデータセンターが求められているのです。
データセンターの高い信頼性を可能にしているのが、高品質な建物設備の保守です。通常の建物や設備と比較して、データセンターは堅牢に作られていますが、かといって保守が不要なわけではありません。堅牢性を維持して、故障や事故の可能性を最小限に押さえるためには、高品質な建物設備の保守が不可欠なのです。
高い信頼性を支える保守スタッフの存在
データセンターには、空調や消火、電気といったさまざまな建物設備が設置されています。そうした設備にはサーバーなどICT機器の安定した稼働を支えるために、高度な技術が投入されています。
例えば、電気設備の1つである無停電電源装置は、停電が起きると瞬時に電力を供給する機能を持ち、ICT機器の電力途絶を防いでくれます。また、空調設備も停電時に最適な室温を保つために、自動で非常用発電機から電力が供給されるなど、データセンター内には多重の工夫が施されています。
しかし、こうした建物設備は、ただ設置しただけでは安心はできません。いざというとき、確実に建物設備の高度な機能を使用するためには、手順や操作方法を熟知した保守スタッフが必要になります。データセンターの保守要員は、設備に関連する公害関係法や消防法といった関係法令についても熟知していなければいけません。なぜなら、設備が大気汚染、騒音の原因になる可能性もあるためです。
建物設備の操作や関係法令に通じた保守スタッフがいてこそ、データセンターの高い信頼性を保つことができます。そして「高品質な建物設備の保守によるデータセンターの高い信頼性」は、日本企業の未来を支えることにもつながっているのです。そのことが明らかになったきっかけが、「DXレポート」です。
DXを阻むITシステムのブラックボックス化
2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」は、産業界に大きな波紋を呼びました。「ITシステム『2025年の崖』克服と DXの本格的な展開」という副題が付けられたレポートは、企業のデジタル対応が遅れれば、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らすものでした。
レポートの中で2025年の崖を引き起こす要因として、最も問題視されたのは古くから使われ続けている ITシステム、いわゆるレガシーシステムでした。日本情報システム・ユーザー協会のアンケート調査では、約8割の企業がレガシーシステムを抱えており、約7割が「レガシーシステムがデジタル化の足かせになっている」と回答しています。
レガシーシステムは老朽化に加え、事業部門ごとに改修が行われるなど場当たり的なカスタマイズにより、複雑化していることも珍しくありません。そうなると、システムの全貌を把握している担当者がいない、あるいは、いたとしても属人化していて、担当者が退職すると維持管理が困難になるというケースもよくあります。こうした状態はブラックボックス化と呼ばれています。
ブラックボックス化されると、部門横断的に社内のデータを活用することは難しくなり、DXに取り組みづらくなります。何よりも、システムトラブルが多発し、貴重なIT人材を「システムの維持管理」に割かなければいけなくなってしまいます。ICT部門が売上拡大といった企業の価値向上に貢献できず、コスト部門に甘んじれば、DXの実現は遠のいてしまいます。
アウトソーシングで社内のリソースを有効活用
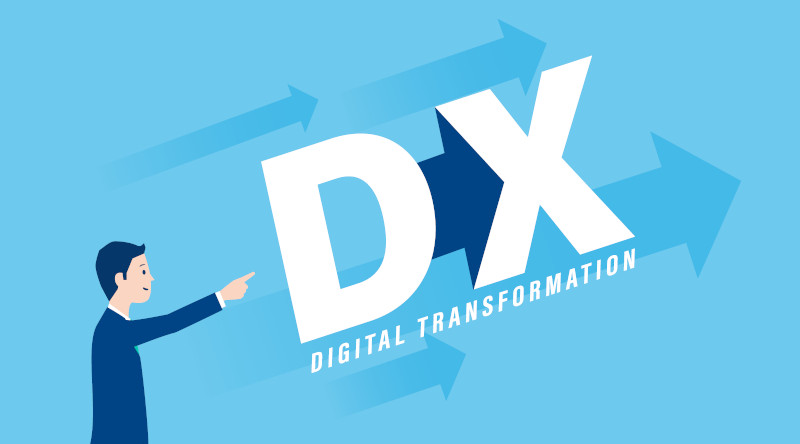
「DX レポート」は非常に厳しい現実を突きつける内容になっていますが、救いがないわけではありません。そこでは、ITシステムを適切にアップデートすることでデジタル対応を進め、企業がDXを実現できれば、2030年には実質GDPが130兆円以上の押し上げることになると試算しています。
経済産業省は、2025 年の崖を克服し、企業のDXを後押しするための資料として「DX推進システムガイドライン」をまとめています。ガイドラインでは、ITシステムの構築について、ガバナンス体制や事業部門の関わり方など、自社内で取り組む際の指針が示されています。
しかし、少子高齢化が進んでいることもあり、IT人材の確保には多くの企業が苦しんでいるのが現状でしょう。実際に、2030年にはIT人材が最大で約79万人も不足するという経済産業省の調査結果もあります。
今後のIT人材の不足を考慮すると、日本企業がデジタル化を進め、DXを実現するためには以下のようなポイントが重要になってきます。
- • レガシーシステムの刷新
- • データセンターなど外部リソースの活用
- • ITシステム運用業務のアウトソーシング
データセンターをはじめとする外部リソースを有効に利用することで、社内の貴重な人材を、新規事業創出や売上拡大といった「攻め」の部分に活用することができます。こうした企業のデジタル化と、それに伴うDXを実現するために、高い信頼性を持ったデータセンターが必要とされているのです。
建物設備の保守では「経験」と「人材」を
重要視したい

先述のように、データセンターの信頼性を保つためには、高品質な建物設備の保守が欠かせません。貴重なデータを守るためには、建物が堅牢でなければいけません。データを格納するサーバーは高熱を発するために、空調で絶えず冷却する必要があります。また、停電時にもサーバーが運転できるように、無停電電源装置(UPS)や自家発電設備の点検も常日頃から欠かせません。
とくにサーバーの発熱量については、機器の高性能化とともに上昇傾向にあります。そうした中で、サーバーや室内を冷却するためには大量の電力が必要ですが、コストの面でも、環境への配慮といった面でも効率化する必要があります。昨今では、高効率空調設備が導入され、非常に高度な室温管理がされるようになっています。管理する範囲が多岐にわたるため、それらの建物設備の保守には幅広いノウハウが必要になりますし、サーバーの高発熱化対応や環境への配慮といった新しい知識も必要です。
日本メックスは NTTグループの一員として、長きにわたり日本の通信を支えてきた実績があります。データセンターにおける建物設備の保守についても経験が豊富ですし、自社のトレーニング施設に高信頼性受電設備を設けるなど、人材の育成にも積極的に取り組んでいます。データセンターは、情報化社会を支え、今後の日本企業のDXを後押しする重要なインフラです。高品質な建物設備の保守を期待するなら、過去の実績に加えて、将来の人材育成に力を入れているかどうかという視点も、判断の材料にしてみてはいかがでしょうか。